
ゲーミングモニターが反応しない場合の対処法について詳しく解説していく。パソコンの電源は間違いなく付いていて稼働しているにもかかわらずモニターが反応しなくて困っている方はぜひ参考にして欲しい。漏れやすいポイントをまとめたチェックリストを公開しているので、それに合わせて対策していけば解決に繋がるはずだ。どうしても解決しない場合はお問い合わせフォームあるいはコメント欄からご連絡いただければと思う。なお、ゲーミングPC自体の電源がつかない方は「ゲーミングPCの電源がつかない時の対処法」を参考にして欲しい。
モニターの問題は原因を特定しにくい!

液晶モニターが反応しない場合、モニターの故障以外にもドライバーなどが原因となることもあり特定することが難しい。様々な要因が考えられるためじっくりと取り組む必要がある。初歩的なミスも含めて一つずつ可能性を潰していって欲しい。私の経験ではPCを初期化した後にモニターが反応しなくなることが多く、さらにグラフィックボードを搭載していると起こりやすいように感じている。
グラフィックボード搭載が一般的なゲーミングPCでは意識しておく必要があるだろう。まず初めに意外と見落としがちなポイントをまとめている。多くの場合、このような初歩的なエラーはほとんどないだろう。しかしながら見落としてしまう代表的なものでもある。この初歩的なエラーで直ったとしたらむしろ安心するところだ。慣れている方でも起こり得る。これで直らなければPCを開いての作業となるため手間が掛かってしまう。
初歩的なミスのチェック項目
モニターが壊れていないか
もし他のモニターを持っているのであればモニターが壊れていないかどうか確認するとよい。他のモニターで問題なく映るのであれば対象のモニターの故障が疑われる。サブモニターを持っていないと故障の判断が難しいので、壊れていない前提でチェックリストを進めて欲しい。
モニターの電源ケーブルがきちんと接続されているか
電源ケーブルの挿し忘れは意外と多い。モニター側にもちゃんと接続されているか確認しておこう。また、個別スイッチ付き延長ケーブルを利用している場合は電源がONになっているかを確認しておくとよい。
電源ケーブルが断線していないか
ケーブルがきちんと刺さっているのにモニターが付かないのであればケーブルの断線を疑おう。可能性としてはそれほど高いわけではないが、引っ張ったりすると断線する可能性がある。そこまで高価なものではないのでスペアを用意しておくとよいだろう。
パソコン側にしっかり接続されているか
グラフィックボードを搭載しているゲーミングPCの場合必ずグラフィックボードの出力端子に接続されているかどうか確認しておこう。マザーボード側に接続するとモニターが映らない。また、ケーブルが外れている可能性もある。机の下に入れている方だと外れてしまっていても気付きにくい。
モニターの電源は入っているか
モニターの電源がONになっているかをチェックしておこう。そんなことは忘れるはずがないと思うかもしれないが、念には念を入れてチェックしておくと安心だ。モニターの電源が入っていればLEDランプが点灯しているはずだ。
モニターの設定は正しいか
接続に合った出力設定になっているかどうかも確認しておこう。例えば、HDMI接続しているのにDisplayPort入力を選択していると正しく描写されない。これはモニター側の設定で簡単に変更可能だ。
ゲーミングモニターが反応しない場合の対処法まとめ
最小構成での起動からの調整
最小構成での起動を試みてみよう。最小構成とはパソコンを起動するのに必要なパーツだけを残して起動することだ。つまり、CPU・CPUクーラー・メモリ1枚・グラフィックボード以外のパーツを取り外す。CPUにグラフィック機能がついているのであればグラフィックボードも取り外そう。最小起動で起動した場合はドライバを更新し最新の状態にしてからグラフィックボードやメモリを搭載していくことで上手くいくことがある。
最小起動でも上手く起動しない、あるいはドライバを更新しても上手く起動しない場合は次のマザーボード(BIOS)の初期化を行わなければならない。こうなるとモニター側の問題ではなくパソコン側の問題だ。そのため、原因を特定するというよりも、不具合の解消という意味合いが強い。
よくあることなので、とりあえず最小起動で正しくパソコンが起動するかを確認したい。メモリを追加したり、グラフィックボードを交換したりした際に発生しやすいように感じる。最小起動はパーツ交換時に生じやすく、自作すると最初の立ち上げは最小起動が推奨されている。突然モニターが映らなくなった際の解決策としては少し弱い気もする。正常に使用できていたのに突然表示されなくなった場合は、別の方法も合わせて確認してほしい。
マザーボード(BIOS)の初期化

最終手段としてマザーボードの初期化を行う。それほど難しいことではないので初心者の方でも行いやすい。筆者はこの方法で解決した。マザーボードに搭載されているボタン電池を外して1分~5分程度放置する。ボタン電池を取り付けて起動してみるとBIOSが初期化され、不具合が解消されることがある。ボタン電池が見つけにくい場所にあるマザーボードの場合は注意が必要だ。
グラフィックボードの影に隠れていることもあり、私自身も見つけるのに時間が掛かってしまった。BIOSの初期化は深刻なエラー等での対策としても有効なので覚えておいても損はない。初期化を行うとCMOS情報がクリアされるため、BIOSに保持されている情報が消去される。時計の設定やBIOSの設定も初期化される。それ自体にデメリットはないが、BIOSのアップデート情報もクリアされることがある。
また、マザーボードによってはマザーボードに接続された電源を全て外して様子を見る必要がある。別の方法としてCMOSクリア端子をショートさせる方法も一般的だ。ただ、端子をショートさせるという言葉から、慣れていない方は敬遠しがちだ。様々な方法があるということだけ覚えておいてほしい。まずは電池を抜いてみて様子を見るのが容易な手法だ。
パソコンの放電を行う
パソコンの不具合対策として、昔からあるのが放電だ。やり方は簡単だが、それなりに時間を要する。上記の手法で改善されなかった場合の最終手段として考えたい。まずはパソコンの電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。その後、電源ボタンを数回押してそのまま放置する。放置時間は1時間程度が推奨されている。実際に放電を行った時は15分程度だったが、うまくパソコンが起動した。
放電については、必要としない電気が帯電することで、パソコンに搭載されているパーツがうまく起動しなくなる。放電を行うことで帯電がなくなり、うまく機能するようになる。この帯電状態は、ある日突然症状として現れる。パソコンが壊れたのではないかと思ってしまうほどだ。放電を知らない人も多く、こんな簡単なことで直るわけがないと決めつけないようにしたい。筆者は初めて放電を行うことになったとき、ほぼ疑いの半信半疑だった。
それで改善して以降は、最終手段としてよく用いる。放電が必要になる頻度は明確にはなっていない。体感としては1年~2年に1回程度だろうか。パソコンの使用時間、頻度などの影響がある。突然パソコンがうまく起動しなくなった、上記の方法を行ってもモニターがつかない。こうなったら一度放電を試してほしい。
主な症状としては、グラフィックボードが起動してすぐ止まる、グラフィックボードが起動していないなどがある。マザーボードに搭載されているパーツがうまく機能しなくなる。他に原因があることもあり、放電で改善するとは限らない。一つの方法として覚えておいて損はない。
ゲーミングモニターに関するよくある不具合
モニターのリフレッシュレートを240Hzに設定できない
| 解像度 | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| HDMI 2.1 | 240Hz | 240Hz | 120Hz |
| HDMI 2.0 | 240Hz | 120Hz | 60Hz |
| HDMI 1.3 / 1.4 | 120Hz | 60Hz | 30Hz |
| HDMI 1.0 – 1.2 | 60Hz | 30Hz | 非対応 |
| DisplayPort 2.0/ 2.1 | 540Hz | 240Hz | 144Hz-240Hz |
| DisplayPort 1.4 | 360Hz (DSC 540Hz) |
240Hz | 120Hz (DSC 144Hz) |
| DisplayPort 1.3 | 360Hz | 240Hz | 120Hz |
| DisplayPort 1.2 | 240Hz | 165Hz | 75Hz |
| DisplayPort 1.0 / 1.1 | 144Hz | 60Hz | 30Hz |
モニターが240Hzに対応しているのに60Hzしか設定できないことがある。この場合入力端子の規格があっていなかったり、パソコンとモニターをつなぐケーブルの規格が対応していなかったりする可能性が疑われる。購入前にパッケージに記載されている規格を確認してほしい。パソコンとモニターをHDMIで接続している場合、HDMIケーブルの規格はHDMI 1.3以上でなければ144Hzに設定できない。HDMIで240Hz出力をするにはHDMI 2.0以上が必要だ。
今はあまり見かけないものの、安価なHDMIケーブルは規格が追い付いていないことがある。DisplayPortは1.2以上であれば240Hzに対応可能だ。240Hzを超えるリフレッシュレートに対応したモニターの場合は、DisplayPortでの接続が推奨されている。そのモニターが対応する最高のリフレッシュレートはDisplayPortでしか出せないことがあるからだ。それぞれの対応するリフレッシュレートは上記の表で確認してほしい。
最新の規格なら、240HzまではHDMIでもDisplayPortでも対応できる。リフレッシュレートをモニターが対応している最大数値に設定できない原因は、そのほとんどがケーブルの規格によるものだ。少し古いゲーミングモニターには、HDMI端子がないモデルもある。その際、モニターへの入力がDVI-Dになると、今度はパソコン側にDVI-D端子がない。
そこで、DVI-DケーブルにHDMI出力に変換するコネクターをつけると、リフレッシュレートは60Hzが最大になる。これと似たようなもので、片方がHDMI端子、もう片方がDisplayPort端子のようなケーブルでも60Hzが最大になる。変換を行うことで出力に制限がかかるので、必ず使用するケーブルはHDMIかDisplayPortで統一してほしい。変換コネクタや入出力がそれぞれ異なるケーブルはトラブルの要因となる。
Netflixやプライムビデオ視聴中に一瞬モニターが消える
複数枚のモニターを利用している方に起こりやすい症状だ。動画を開始する前やブラウザ・アプリケーションを閉じる際に一瞬だけモニターが消えることがある。これはHDCPという著作権保護の機能が働くことで起こる症状である。映画をキャプチャーできないようにする保護機能で、映像キャプチャーソフトも強制終了することがある。
Netflixやプライムビデオを視聴すると、NVIDIAのインスタントリプレイも強制的にオフになる。これに連動してモニターも一瞬真っ暗になる。この症状自体はすぐに戻るのでそれほど問題があるわけではない。しかし、毎日映画を見るたびにモニターが切れたり、キャプチャーソフトがオフになったりするのは気になってしまう。
対処法としては接続している端子を変更することだ。おそらく多くの方はHDMIあいはDisplayPortのいずれかを使用しているはずだ。一度DVI-Dに変更してみるとよい。問題は、このDVI-Dに対応したモニターは年々減少傾向にあることだ。変換コネクターを使用することで直ることがある。HDMIからDisplayPortに変更しても直った例もあるので、一度接続端子を変更してみてほしい。
なお、著作権を保護するためのHDCPを解除することは違法ではない。コストはかかるが、キャプチャーボードや分配器を使えば解除できる。どうしても気になる場合の最終手段に考えておこう。
当記事のまとめ
当記事では、液晶モニターがうまく起動しない場合の対象方法についてまとめた。中上級者の方でも躓いてしまうことがあるのでぜひチェックして欲しい。まずは、配線に問題はないか、モニターの電源は入っているかなど初歩的なミスがないかどうか確認するとよい。
それらに問題がなければPCの最小起動及びマザーボードの初期化を行おう。これらの対策を行っても解決しない場合はコメント欄あるいはお問い合わせフォームより連絡をしていただければと思う。


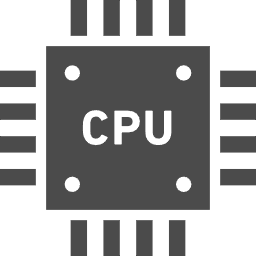
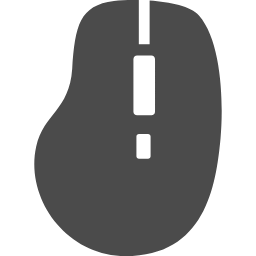







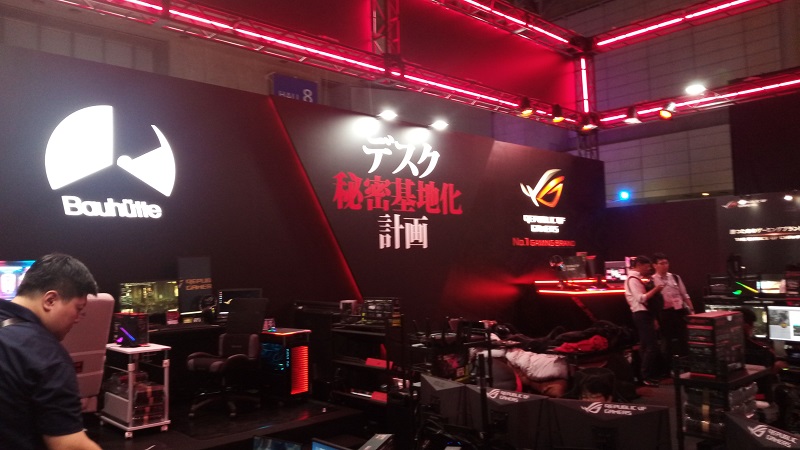
PS5でゲーミングモニターを使用していましたが、起動してもうっすら明るくなるだけで何も映りません。配線を新しいものに変えても、他のゲーム機に繋いでも同じです。購入から10ヶ月ですが保証書を無くしてしまっていて、実費修理か再購入か迷っています。
本体故障以外原因はありますか?
記事の主旨と違うかもしれませんが、初めてデスクトップ買ったときにした初心者すぎるミスで、配線をマザボ側?に挿して点かないなーと1日悩んだことがあります。
その後、その下のグラボに挿さなきゃいけないことに気づいたことを挙げときます。